腹部大動脈瘤の治療について知っておきたい基本情報【2025年版】
腹部大動脈瘤は、破裂すると命に関わる危険な病気ですが、多くの場合は無症状で進行します。そのため、早期発見が非常に重要です。定期的な検査や画像診断によって状態を把握し、必要に応じて外科的治療やステント治療が選択されます。日本では高齢化の影響により増加傾向にあり、専門の医療機関での管理が推奨されています。生活習慣の改善や高血圧管理も重要な予防手段です。詳しい検査内容や治療法は、以下をご確認ください。
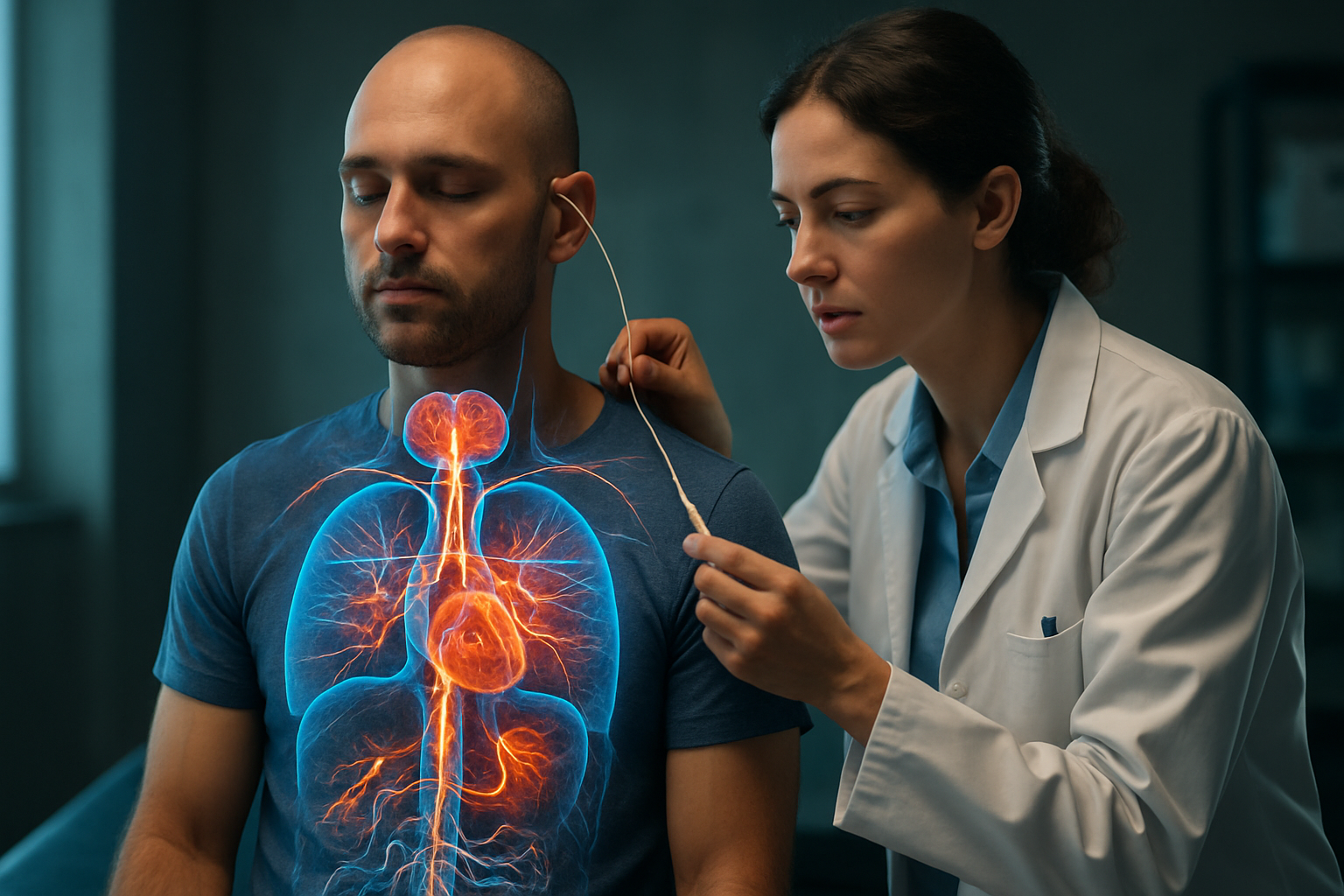
腹部大動脈瘤の最も危険な合併症は「破裂」です。大動脈瘤が破裂すると、短時間で大量出血を起こし、緊急手術を行っても致死率は40〜50%に達します。しかしながら、破裂前に発見された場合の計画的な手術の成功率は95%以上と高いため、早期発見と適切な管理が非常に重要となります。
危険因子としては、65歳以上の男性、喫煙歴、高血圧、動脈硬化性疾患の家族歴などが挙げられます。特に喫煙者は非喫煙者と比較して発症リスクが約3〜5倍高くなるとされています。
診断や検査の方法とその重要性
腹部大動脈瘤は多くの場合、無症状で進行するため、定期的な検査が重要です。診断には主に以下の検査方法が用いられます。
-
超音波検査:非侵襲的で簡便な検査方法であり、スクリーニングに最適です。大動脈の直径を測定し、瘤の有無や大きさを評価します。
-
CT検査:より詳細な情報が得られる検査法で、瘤の正確な大きさ、形状、周囲の臓器との関係などを把握できます。特に手術前の評価に重要です。
-
MRI検査:放射線被曝がなく、CT検査と同様の情報が得られますが、費用や検査時間などの観点からCT検査が優先されることが多いです。
日本循環器学会のガイドラインでは、50歳以上の男性や喫煙歴のある女性など、リスクの高い方には定期的な超音波検査によるスクリーニングが推奨されています。特に65歳以上の男性では、一度検査を受けることが強く勧められています。
瘤が見つかった場合、その大きさや拡大速度に応じて経過観察や治療方針が決定されます。一般的に直径が5.5cm以上、または6ヶ月で0.5cm以上拡大する場合は治療の対象となります。
治療方法の種類と適応の違い
腹部大動脈瘤の治療は、瘤のサイズ、場所、患者の全身状態などを考慮して選択されます。主な治療法は以下の3つです。
-
経過観察:直径が小さい瘤(一般的に4.0cm未満)の場合、定期的な画像検査による経過観察が選択されます。3〜12ヶ月ごとに超音波検査やCT検査を行い、瘤の拡大速度をモニタリングします。
-
開腹手術(人工血管置換術):従来からの標準的な治療法で、開腹して瘤を切除し、人工血管に置き換えます。全身麻酔下での大手術となりますが、長期成績が確立されています。若年者や腎動脈下の単純な形状の瘤に適しています。
-
ステントグラフト内挿術(EVAR):カテーテルを用いて足の付け根から挿入したステントグラフト(金属の骨組みに人工血管を覆ったもの)を瘤内に留置する低侵襲治療です。開腹手術に比べて入院期間が短く、高齢者や合併症の多い患者さんに適しています。
治療法の選択にあたっては、患者の年齢や全身状態、瘤の形態などを総合的に判断します。例えば、75歳以上の高齢者や心肺機能が低下している患者さんではステントグラフト内挿術が選ばれることが多く、一方で若年者や長期耐久性を重視する場合には開腹手術が選択されることがあります。
近年は技術の進歩により、ステントグラフト内挿術の適応が拡大しており、日本でも多くの施設で第一選択として行われるようになってきています。しかし、解剖学的に不適な場合や長期的な耐久性に課題があることも認識されています。
日常生活で注意すべき点や予防に関する情報
腹部大動脈瘤の予防や進行抑制には、生活習慣の改善が重要です。以下に主な注意点をまとめます。
-
禁煙:喫煙は最大のリスク因子であり、禁煙することで発症リスクや進行速度を大幅に低減できます。
-
血圧管理:高血圧は瘤の進行を加速させるため、適切な血圧コントロールが必要です。降圧薬の服用と共に、塩分制限、適度な運動、ストレス管理なども重要です。
-
脂質管理:動脈硬化の進行を抑えるため、コレステロール値の管理が重要です。必要に応じて、スタチンなどの薬物療法が検討されます。
-
適度な運動:突然の激しい運動は避け、ウォーキングなどの有酸素運動を医師の指導のもとで行います。特に瘤が大きい場合は、重い物の持ち上げなど腹圧がかかる動作に注意が必要です。
すでに腹部大動脈瘤と診断された方は、定期的な検査を欠かさず受けることが最も重要です。また、突然の腹痛や背部痛が生じた場合は、瘤の急速な拡大や破裂の可能性があるため、すぐに救急受診してください。
国内の腹部大動脈瘤治療の医療機関と費用
腹部大動脈瘤の治療には専門的な技術と設備が必要なため、経験豊富な医療機関での治療が望ましいです。日本国内では以下のような医療機関が高度な治療を提供しています。
| 医療機関名 | 特徴 | 治療実績 | 概算費用(保険適用時) |
|---|---|---|---|
| 国立循環器病研究センター | 血管外科専門医が多数在籍、先進的治療 | 年間200例以上 | 開腹手術:30-50万円、EVAR:70-120万円 |
| 東京大学医学部附属病院 | 複雑症例への対応、研究実績 | 年間150例以上 | 開腹手術:30-50万円、EVAR:70-120万円 |
| 大阪大学医学部附属病院 | ステントグラフト治療の豊富な経験 | 年間180例以上 | 開腹手術:30-50万円、EVAR:70-120万円 |
| 榊原記念病院 | 低侵襲治療に特化 | 年間120例以上 | 開腹手術:30-50万円、EVAR:70-120万円 |
※価格、料金、費用の見積もりについては、最新の情報に基づいていますが、時間の経過とともに変更される可能性があります。経済的な決断を下す前に、個別に調査することをお勧めします。
治療費用は健康保険が適用されますが、ステントグラフト内挿術(EVAR)は使用する機材が高額なため、開腹手術よりも患者負担額が大きくなる傾向があります。ただし、入院期間が短く、合併症のリスクも低いため、総合的なコストパフォーマンスでは有利な場合もあります。また、70歳以上の方は高齢者医療制度により、窓口負担が軽減されます。
まとめ
腹部大動脈瘤は、適切な管理と治療によって良好な予後が期待できる疾患です。無症状で進行することが多いため、リスク因子を持つ方は定期的な検査を受けることが重要です。治療方法は瘤のサイズや患者の状態によって選択され、開腹手術とステントグラフト内挿術のどちらも高い成功率を誇ります。日常生活では、禁煙、血圧管理、脂質コントロールなどの生活習慣改善が進行抑制に効果的です。専門医による適切な指導のもと、自身の状態に合った治療法を選択することが大切です。
※本記事は情報提供のみを目的としており、医学的アドバイスとして捉えないでください。個別の治療やケアについては、必ず資格を持つ医療専門家にご相談ください。




